「目を覚ましたら、世界が壊れていた」──そんな物語が、あなたの“普通”を根こそぎ揺さぶる。
Netflixの話題作『今際の国のアリス』。いつもの渋谷、いつもの日常。けれどその翌朝には、人の気配は消え、街は静まり返っている。電車は走らず、スマホは沈黙し、スクランブル交差点だけが無言で光を放っている──。
有栖良平(アリス)は、怠惰で曖昧な日々を送っていた青年。家族にも社会にも居場所を感じられず、ゲームの世界に逃げ込んでいた彼が、友人のチョータ・カルベとともに渋谷に足を踏み入れたその瞬間から、彼らの運命は“げぇむ”という名の極限へと引きずり込まれる。勝てば生き、負ければ死――ルールはいたってシンプル。しかしその中には友情、裏切り、信念、恐怖、そして“生きる意味”への問いがぎっしり詰め込まれている。
このドラマは、1話から最終話まで、ひとつの流れとして“あらすじ”を追うことで、その背後に潜むテーマや伏線にも触れられる構成になってる。だからこの記事では、**ドラマ1話~最終話までのあらすじを丁寧にまとめつつ**、その中で見逃したくないポイントや感情の揺らぎも一緒に味わっていきたい。原作との比較も交えながら、「ここが変わった」「ここがぐっと心を掴む」瞬間を一緒に追っていこう。
それでは、扉を開けよう。あなたを、“今際の国”への旅へ誘う、あらすじまとめガイド──始まるよ。
- ドラマ『今際の国のアリス』1話から最終話までのあらすじを時系列で理解できる
- 物語を通じて描かれる「ビザ制度」や「げぇむ」の仕組みが整理できる
- 主要キャラクターの行動と心理をあらすじから把握できる
- 原作漫画との違いや、ドラマならではの演出の特徴がわかる
- シーズン3を楽しむための復習ポイントが整理できる
ドラマ「今際の国のアリス」とは?基本情報と作品背景
| 『今際の国のアリス』基本データをサクッとおさらい! |
|---|
| ・Netflixが世界同時配信したオリジナルドラマ ・原作は麻生羽呂による漫画『今際の国のアリス』 ・主演は山﨑賢人(アリス役)、土屋太鳳(ウサギ役) ・監督は佐藤信介、VFXとロケで“無人の渋谷”を完全再現 ・シーズン1は2020年配信、シーズン2は2022年、シーズン3は2025年配信予定 ・世界のNetflixランキングでも上位を獲得、国際的に人気 |
ドラマ『今際の国のアリス』は、Netflixが全力で仕掛けた世界級のサバイバルスリラー。
原作は麻生羽呂による漫画で、国内外でカルト的な人気を誇っていました。その漫画が「どうせ実写化したら残念になるんでしょ?」という視聴者の不安を軽々と飛び越え、むしろ「これが正解!」と言わせる完成度で映像化されたのがこの作品なんです。
監督は、映画『GANTZ』や『キングダム』でも知られる佐藤信介。渋谷のスクランブル交差点をまるごと封鎖し、“無人都市”をリアルに再現したロケはまさに伝説レベル。VFXも惜しみなく投入されていて、「え、これドラマのクオリティ超えてない?」と誰もが二度見したほどです。
主演は山﨑賢人がゲームオタク気質の青年・アリスを演じ、土屋太鳳がタフで聡明なウサギを熱演。ほかにも森永悠希(チョータ)、町田啓太(カルベ)、村上虹郎(チシヤ)、三吉彩花(シブキ)、仲里依紗(クイナ)など豪華キャストが続々登場。推しを見つけて「わ、このキャラ応援したい!」ってなる人、きっと続出します。
さらに注目なのは、世界配信のインパクト。2020年にシーズン1が公開されるやいなや、アジアを中心に爆発的ヒット。Netflixのランキングでも上位に食い込み、「日本発のドラマってここまでできるんだ」と国際的に評価されました。2022年のシーズン2ではさらに規模が拡大し、そして待望のシーズン3が2025年に配信予定。つまり今がまさに、振り返りと予習のベストタイミングなんです。
…とまぁ真面目に語りましたが、正直この作品、情報だけでもうワクワクしません?渋谷が消える、げぇむで生き残り、仲間とぶつかり合い、そして世界の真実に迫る…。ひより的に言わせてもらうと、「人生で一度は味わうべき、心臓バクバク体験」です(笑)。
第1話~第3話:無人都市の恐怖と“げぇむ”の始まり
| 序盤エピソードで描かれる“日常崩壊”と初めての死のゲーム |
|---|
| ・渋谷が突如として無人化する衝撃のオープニング ・主人公アリスと友人カルベ・チョータが閉じ込められる ・「げぇむ」のルール説明とトランプのマークによる分類 ・初めてのゲームで“命の重み”を突きつけられる ・仲間との絆が試される最初の大きな分岐点 |
ドラマ冒頭、第1話から渋谷のスクランブル交差点が一瞬で無人化するシーンは衝撃そのもの。いつもは人でごった返す街が、信号だけを残してシーンと静まり返っている光景は、まるで“世界が壊れた瞬間”を映し出しているようでした。視聴者も「え、なにこれ?」と一気に作品世界へ引き込まれます。
アリス(山﨑賢人)、カルベ(町田啓太)、チョータ(森永悠希)の3人は、成り行きで不思議な建物に入り込みます。そこで突然表示される文字──「WELCOME TO THE GAME」。彼らは“げぇむ”と呼ばれる死のゲームに巻き込まれてしまいます。
ゲームのルールはシンプル。でも、そのシンプルさが逆に怖い。
勝てば“ビザ”が発行され、生き延びられる。負ければ即死。
しかもその死は、天空から降り注ぐレーザーによって一瞬で訪れる…という残酷な仕様。これで一気に「命の重さ」が視聴者に突きつけられます。
ゲームにはトランプのマークでジャンル分けがされているのも特徴。
・♠(スペード):体力勝負のアクション系
・♥(ハート):信頼や心理を揺さぶる精神戦
・♦(ダイヤ):知恵と論理力を試す知能戦
・♣(クラブ):協力プレイがカギとなるチーム戦
序盤のげぇむでは、彼ら3人の友情と信頼が強く試されます。普段は冗談を言い合っていた仲なのに、死を前にすると心の奥が暴かれていく。ゲームの緊張感と心理的な揺さぶりの両方が重なって、視聴者も「誰を信じればいいんだ?」と一緒に不安を感じる構造になっているんです。
第3話までで描かれるのは、アリスが「ただの遊び」から「命懸けの現実」へ踏み込む瞬間。仲間の犠牲も重なり、笑っていた日常が一変していく。ここから物語は加速し、誰もが「もう後戻りできない」と悟るのです。
この序盤の展開は、『今際の国のアリス』という作品の魅力を一気に凝縮したもの。日常の崩壊、ゲームの恐怖、人間関係のひずみ──そのすべてが一気に観る人の心をつかんで離さないんです。
第4話~第6話:ビザ制度と拠点“ビーチ”への道のり
| 中盤で描かれる“生き延びるためのルール”と新たな人間模様 |
|---|
| ・“ビザ制度”によってゲームが強制される仕組みが明らかに ・命の残り時間が減っていく焦燥感が描かれる ・新たな生存者との出会いがストーリーを複雑に ・“ビーチ”という拠点が登場し、秩序と混沌が交錯する ・集団行動による利害の衝突が物語を加速させる |
第4話からは、この世界の根幹を成す“ビザ制度”の恐ろしさが明かされます。
ゲームをクリアするたびに残り日数が表示される「ビザ」が与えられますが、その期限が切れた瞬間、天空からレーザーが落ちてきて即死…。つまり、「ゲームをやめる=死」という逃げ場のないルール。視聴者も「え、休むことすら許されないの!?」と絶望感を味わうことになります。
この頃からアリスは、ただ怯える若者ではなく“生き延びるために考え、決断する人間”へと変化していきます。友人の死を背負い、涙を流しながらも前に進む姿は、観る人の胸を強く打ちます。
そして中盤の最大の転換点が、“ビーチ”の登場。
ビーチとは、廃ホテルを拠点にした生存者たちの共同体。プールで音楽を流し、酒を飲みながら過ごす一見“楽園”のような空間ですが、その裏にはカードを集めるための冷酷な支配構造があります。
ここでは「集団で生き残る」ことの難しさが描かれます。協力してカードを集めようとする者、権力を握ろうとする者、利用される者──。それぞれの思惑が絡み合い、単なるサバイバルから政治的な駆け引きへと舞台がシフトしていくのです。
第4〜6話は、物語が一気に広がる中盤の山場。アリスとウサギが仲間を増やしながらも、人間の欲望や裏切りに翻弄される姿は、「ただのゲームの物語じゃない」と実感させられる展開です。
──そして、この“ビーチ”での出会いと衝突が、やがて物語をクライマックスへと導く大きな伏線になっていくのです。
第7話~最終話:決戦と真実の暴露(ネタバレ注意)
| 最終局面で描かれる“心臓バクバク”の決戦と世界の核心 |
|---|
| ・「王カード」を巡る壮絶なゲームが始まる ・仲間の犠牲が相次ぎ、アリスとウサギの絆が最大の試練に ・ゲームを通じて人間の極限心理があらわになる ・ついに“今際の国”の真相が明かされる ・余韻を残す結末が視聴者に衝撃を与える |
第7話以降、物語は一気にクライマックスモードに突入します。
“王カード”を象徴する最強のゲームが登場し、それまで以上に理不尽で過酷なルールがプレイヤーを追い詰めていきます。
ここからの見どころは、なんといっても仲間の命が一人、また一人と失われていく過程。ただのキャラ消費じゃなく、それぞれの信念や想いを背負った別れが描かれるからこそ、観ている側も胸がギュッと締めつけられるんです。推しが出ている人は、心の準備をお忘れなく(ほんと、ハンカチ推奨)。
特にアリスとウサギ、この二人の関係は最大の試練を迎えます。生き延びたい、でも守りたい、でも信じたい…そのジレンマに揺れながらも、互いを見つめる視線がもうエモすぎて。ここは「ただのデスゲーム」じゃなくて「人間ドラマ」として世界に評価された理由が詰まってます。
そしてついに物語は“今際の国”という舞台そのものの真相に迫ります。
「なぜ渋谷は無人化したのか」「ゲームの目的は何なのか」──その答えが明かされる瞬間は、きっとあなたも画面の前で「そう来たかぁ!」と声を出すはず。
最終話のラストは、ただのカタルシスで終わらせずに、視聴者に余韻と問いかけを残す構成。すべてが明らかになったようで、まだどこかに“謎”が残っているような不思議な感覚。エンドロールを見終わった後、ふと「生きるってなんだろう」と考えさせられるのが、この作品のすごさです。
──というわけで、シーズン1の最終話までを観終わったとき、心臓はバクバク、頭はクラクラ、そして口から出るのはきっと「続きはよ!」の一言(笑)。それこそが、この作品が世界中で愛された証拠なんです。
原作漫画との差異まとめ:なぜ変えた?その意図とは
| ドラマと原作の違いをチェック!改変の理由とは? |
|---|
| ・ゲームの順番や内容がドラマ用に再構成されている ・キャラクターの内面や背景がより丁寧に描かれる ・一部キャラクターの役割や展開がオリジナル要素で変更 ・映像表現で心理的インパクトを強化 ・結末の描き方に細かな違いが存在する |
「原作とドラマ、どっちが正解?」──ファンなら一度は考えたことがあるはず。
でも実際はどちらも“正解”なんです。というのも、ドラマ版『今際の国のアリス』は、原作をリスペクトしながらも映像ならではの魅力を出すために、あえて違いを取り入れているんですよ。
まず大きいのがゲームの順番。原作ではこのタイミングで出てきたゲームが、ドラマでは後ろに回されたり、演出が変わっていたりします。これはドラマ特有の“1話ごとの緊張感”を高めるための調整で、「観る手を止めさせない」ための工夫なんですね。
次にキャラクターの描写。アリスやウサギはもちろん、チシヤやアンといったサブキャラの内面も丁寧に描かれています。原作だとテンポ優先で流れてしまった部分が、ドラマでは役者の表情や演技でじっくり表現される。これが「推しキャラ尊い…」とファンの心をさらに掴んでるんです。
さらに、ドラマ版にはオリジナル要素も追加されています。たとえばセリフのニュアンスやサイドストーリーが微妙に変えられていて、「あ、この展開はドラマ版だけだ!」という発見があるんです。原作既読勢も「おお、そう来るか」と楽しめる仕掛けになってます。
映像表現の違いも大きなポイント。暗闇でのライトの使い方、赤いレーザーの緊張感、街のスケール感…。紙の上では想像するしかなかった部分が、ドラマでは“心臓に直接刺さる演出”として描かれているんです。
そして結末の描き方。大筋は同じでも、演出やセリフの違いによって「ドラマの方がエモさが増してる!」と感じる人も多い。逆に「原作の方が余韻が深い」と思う人もいるでしょう。どちらも味わうことで、『今際の国のアリス』の世界がより立体的に見えてきます。
──つまり、原作ファンもドラマファンも、両方チェックしてこそ100%楽しめる作品!「違い探し」感覚で観ると、もはや2度おいしいんです(笑)。
あらすじを読むと見えてくるテーマと魅力
| “物語の奥に隠れている本当のメッセージ”を読み解こう |
|---|
| ・あらすじを追うだけでなく、その裏に流れるテーマを感じられる ・「生きる意味」を突きつける問いが全編を貫いている ・キャラクターの選択は視聴者自身への問いかけでもある ・伏線や余白が視聴後に語り合いたくなる魅力を生んでいる ・サバイバルを超えて“人間賛歌”に到達する物語 |
『今際の国のアリス』を1話から最終話まで振り返ると、ただの“死のゲーム”では終わらないことに気づきます。
そう、この作品の根底に流れているのは「生きるとは何か?」という問いなんです。
アリスは最初、何となくゲームに逃げて生きていた青年。だけど“今際の国”では、生き残るために他人を信じるか裏切るか、命を懸けて決断しなければならない。その姿は、実は私たちの日常にも通じています。「この選択、本当に正しいのかな?」と不安になるあの瞬間と、実はすごく似てるんです。
ウサギは「誰かと一緒に生きる意味」を体現するキャラクター。彼女がアリスに差し伸べる手は、観ている人にとっても「あなたも一人じゃないよ」と語りかけてくるよう。だから視聴後、多くの人が「ウサギ推せる…!」ってなるのは必然なんです(笑)。
さらに面白いのが、ドラマの中に散りばめられた伏線や余白。ゲームのルール、登場人物の背景、そして世界の仕組み…ひとつひとつが「これってどういう意味?」と観終わった後も語り合いたくなる仕掛けになっています。SNSでの考察合戦が盛り上がったのも納得です。
そして最終話まで進むと、気づくんです。
この物語は、ただ人が死んでいくゲームの話じゃなくて、「人はなぜ生きるのか」「人はどうして人を信じるのか」という、壮大なテーマを描いていたんだと。
──つまり『今際の国のアリス』は、デスゲーム作品を装った“人間賛歌”なんです。
観終わった後、きっと誰もが心のどこかで「自分ももっと生きたい」「誰かと繋がりたい」と思うはず。あらすじを追うだけで、そのテーマに自然と触れられる──それこそが、この作品の最大の魅力なんです。
だから私は声を大にして言いたい。
「今際の国のアリス」は、ただ“観る”んじゃなくて“感じる”ドラマなんです!
- 『今際の国のアリス』は“日常崩壊”から始まるサバイバルスリラーで、1話から最終話まで緊張感MAX
- ビザ制度とげぇむのルールが物語の中核を握り、人間ドラマを際立たせている
- シーズン終盤は「王カード」を巡る決戦と世界の真相が描かれ、余韻を残す結末に
- 原作漫画との違いはゲーム構成や心理描写にあり、両方を楽しむことで世界観が立体化する
- テーマは「生きる意味」と「人とのつながり」。ただのデスゲームを超えた人間賛歌
- シーズン3配信も予定されており、今こそ復習と考察の絶好のタイミング
「もっと深掘りしたい!」そんなあなたのために、関連記事を用意しました。
あらすじを押さえた今だからこそ楽しめる考察や裏話もチェックしてみてね♪
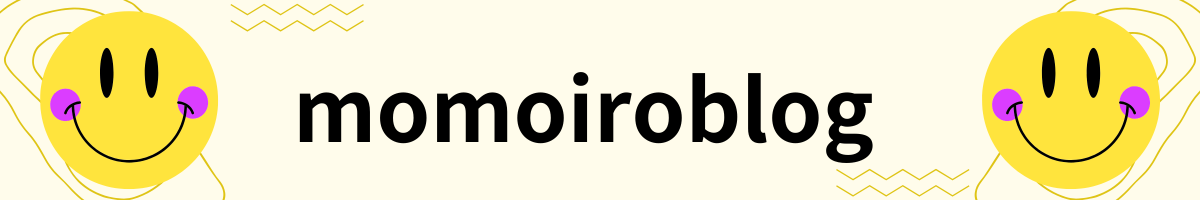







コメント